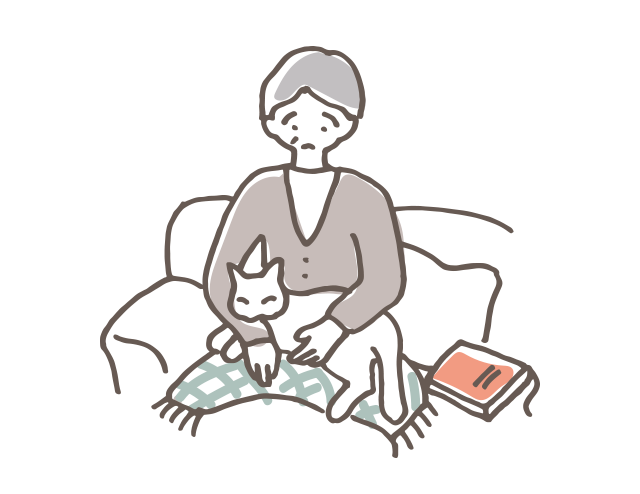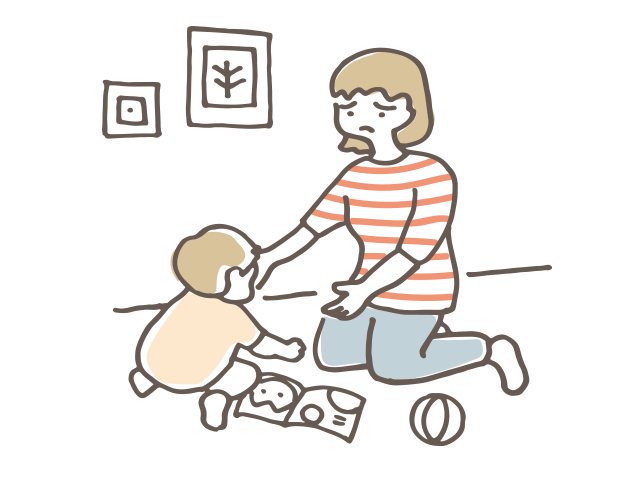成年後見・相続・終活
■成年後見
高齢になり、一人で物事を判断したり、財産を管理することが不安になった場合に利用できる制度として、成年後見制度があります。成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、ご本人の意思決定を支援します。
老後に備え、予め、任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約などを締結し、どなたに何を依頼するか、契約で定めることも可能です。
■相続・終活(遺言)
お亡くなりになった方の財産は、法定相続人が、法定相続分に応じて、取得することが原則です。
特定の相続人に特定の財産を遺したい、相続に対する自分の思いをきちんと相続人に対して伝えたい、相続人間で揉めてほしくない、そのような場合には、終活の一環として遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。